精神保健福祉法改正で虐待行為の通報義務が課されて、1年が経過しました。
これによって精神科医療の現場はどのように改善されたのでしょうか。
虐待の定義については、看護師などが身体的精神的に追い詰めるような行為である事に変わりはありませんが、その運用については、患者側の訴えによって虐待行為が成立するようになりました。
各施設の運用によるところもありますが、基本的に患者が不満を訴えれば虐待が成立する事になり、通報義務が生じるようになります。
患者側が看護師の指導などについて、意に沿わなければ即虐待が成立する事にもなります。
通報義務者は病院などの施設側となりますが、これにも問題があり、患者に対して特定の看護師などへの不満を訴えるように誘導、つまりは患者を操作して虐待行為をでっち上げる事も可能になります。
その結果、直接患者対応にあたる看護師には疑心暗鬼の状態が生まれて、患者には当たらず触らずの状態となり、指導的関わりが難しい状況もなりました。
虐待行為有無を判断さるのも、普段から看護師と患者の関わりはもちろん、状態を全く把握していない管理事務や看護部の人達が、患者の投書によって判断する形です。
これによって、患者の「言った者勝ち」の状況が生まれ、事実確認する間もなく、虐待行為が成立し看護師が責められる立場になります。
これでは看護師は怖くて患者に関わる事などできません。
その結果、病棟内は患者同士のトラブルや患者の逸脱行為が放置される事となり、安全性の確保が難しい状況です。
20年〜30年前の精神科病院は酷い状況で、患者への物理的暴利行為や、精神的虐待は看護師の「娯楽」として横行していて、とても一般社会での常識として通用するものではなく、タブーとされるものでした。
それに対して現在はその反動とも言える状況で、病棟内の患者同士の安全はもちろん、看護師の安全の確保もままならない状況にあります。
「精神科は楽ぅ〜」などと言ってしまう女性看護師も多くいる精神科病棟ですが、そのあたりの事も少し深掘りしてみるのも決して悪い事ではないように思います。
これによって精神科医療の現場はどのように改善されたのでしょうか。
虐待の定義については、看護師などが身体的精神的に追い詰めるような行為である事に変わりはありませんが、その運用については、患者側の訴えによって虐待行為が成立するようになりました。
各施設の運用によるところもありますが、基本的に患者が不満を訴えれば虐待が成立する事になり、通報義務が生じるようになります。
患者側が看護師の指導などについて、意に沿わなければ即虐待が成立する事にもなります。
通報義務者は病院などの施設側となりますが、これにも問題があり、患者に対して特定の看護師などへの不満を訴えるように誘導、つまりは患者を操作して虐待行為をでっち上げる事も可能になります。
その結果、直接患者対応にあたる看護師には疑心暗鬼の状態が生まれて、患者には当たらず触らずの状態となり、指導的関わりが難しい状況もなりました。
虐待行為有無を判断さるのも、普段から看護師と患者の関わりはもちろん、状態を全く把握していない管理事務や看護部の人達が、患者の投書によって判断する形です。
これによって、患者の「言った者勝ち」の状況が生まれ、事実確認する間もなく、虐待行為が成立し看護師が責められる立場になります。
これでは看護師は怖くて患者に関わる事などできません。
その結果、病棟内は患者同士のトラブルや患者の逸脱行為が放置される事となり、安全性の確保が難しい状況です。
20年〜30年前の精神科病院は酷い状況で、患者への物理的暴利行為や、精神的虐待は看護師の「娯楽」として横行していて、とても一般社会での常識として通用するものではなく、タブーとされるものでした。
それに対して現在はその反動とも言える状況で、病棟内の患者同士の安全はもちろん、看護師の安全の確保もままならない状況にあります。
「精神科は楽ぅ〜」などと言ってしまう女性看護師も多くいる精神科病棟ですが、そのあたりの事も少し深掘りしてみるのも決して悪い事ではないように思います。
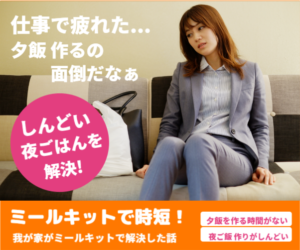
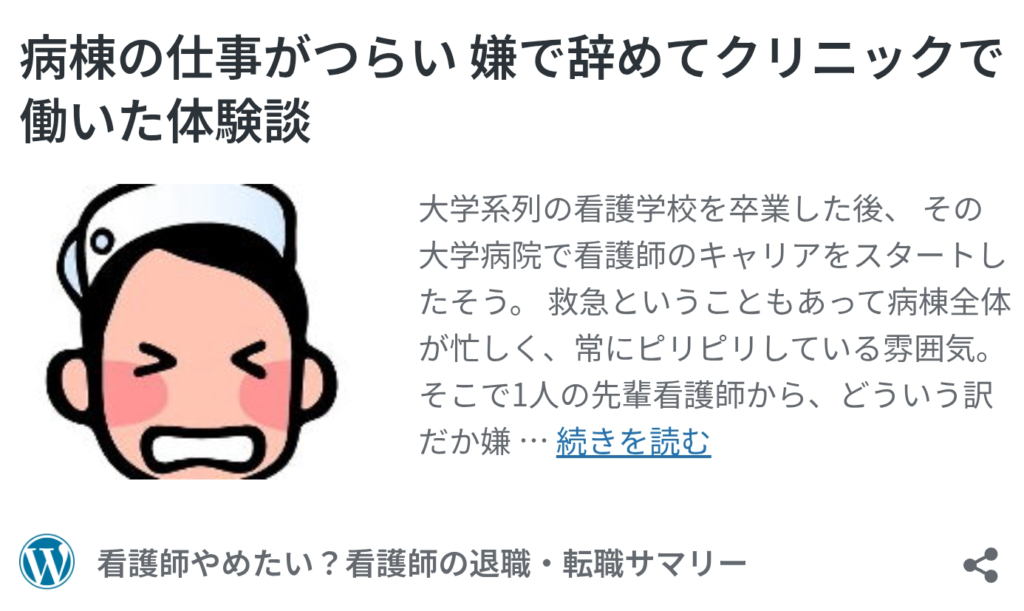

励ましの言葉
物理的、心理的にもサンドバッグ状態で、あらゆる方面からボコられっ放しです。
それもそうなのですが、この一年で現場は余計に疲弊しつつ、荒廃している実感があります。